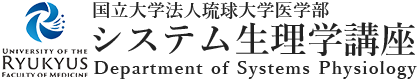琉球大学医学部 システム生理学講座|当教室は排尿生理に着目して、世界的な研究に取り組んでいます。
講座紹介
- トップページ
- 講座紹介
システム生理学講座について
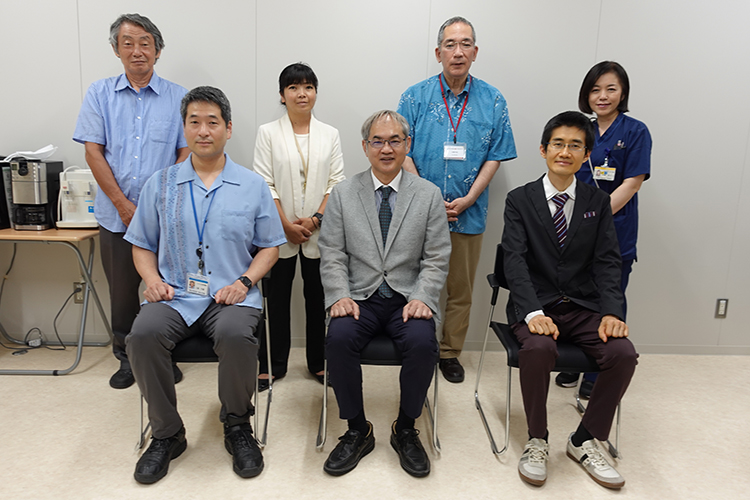

当教室は排尿生理に着目して、世界的な研究に取り組んでいます。
加齢、糖尿病、脳梗塞、パーキンソン病、腹圧性尿失禁といった女性特有の疾患、間質性膀胱炎といった難治性疼痛疾患など様々な病態モデルを用いて排尿障害のメカニズムの解明、創薬の開発を行っています。
排尿は単なる生命現象ではなく、高次脳機能、生体内のホメオスターシスにも関与し、臨床的にも基礎的にも研究の重要性が増してきています。私たちは橋渡し研究を積極的に推進しています。
【大学院での研究指導内容】
- 加齢にともなう自律神経変化と排尿障害機序の解明
- 排尿病態モデルを利用した排尿障害創薬研究
- 難治性骨盤痛を標的とした神経可塑性の研究
- 膜電位の光学的測定法を用いた脳・中枢神経系の機能の研究
- 排尿を起点とした橋渡し研究とイノベーションの開発
- 母子隔離ストレスモデルを利用した排尿機能障害と中枢神経可塑性機序の解明
- マウスモデルを用いた自閉症等社会行動疾患の神経制御機序の研究
【学生講義担当】
- 分子細胞生物学・・・細胞膜、神経による情報伝達の基礎
- 神経科学・・・膜電位、神経伝達、脊髄、記憶、学習といった脳の高次機能
- 人体の構造と機能・・・生体の恒常性維持、腎機能、感覚器のはたらき、生理学実習
- 発生再生医学・・・尿生殖器系の発生
- 医学外国語
教授挨拶

システム生理学講座 教授 宮里 実
琉球大学大学院医学研究科システム生理学講座のホームページへようこそお越しくださいました。当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。この度、当ホームページをリニューアル致しました。多くの医学部のホームページが研究者向けであるなか、当ホームページは一般の方、学生、企業の方を対象にしています。なぜなら、私たちが目指すゴールが、「研究」と「教育」の成果を広く社会に還元すること、何よりも皆さまによりよい生涯を送ってもらいたいからです。
生理学は、ノーベル医学生理学賞 というように、「人体の生命現象」を追究する学問です。システムとは、社会では組織のことですが、医学では臓器や神経のことを意味します。システム生理学は、医学の根幹を支えているところといえます。私は、26年間臨床医(泌尿器科医)として勤め、平成31年(令和元年)にシステム生理学講座(基礎講座)の教授に転身した経歴をもちます。臨床医として働く中で、「システムとしての排尿機能」に興味をもちました。「排尿」しない人間はいません。一般に、「自立した排尿」ができる期間が、健康寿命(ヒトらしく生きる)といわれます。また、臨床医として多くの癌や慢性疾患の患者さんと接するなかで、「痛み」がなく最期を迎えることがいかに幸せなことか学びました。残りの医師人生を、「痛み」と「排尿」の研究に捧げる決意をしました。母校の学生には、生理学を通して真理を伝えたいと思います。
当講座は、初代寺嶋眞一教授、二代目酒井哲郎教授の後を受け、平成31年(令和元年)に宮里が三代目として引き継ぎました。優秀なスタッフ、大学院生、そして「宮里ラボ」の卒業生が当講座の中核となり、すでにいくつものこれまでにない研究が立ちあがっています。臨床と基礎をつなぐ「橋渡し研究」、研究者と企業をつなぐ「産学連携」がこのホームページには詰まっています。研究は研究者のものではありません。私たちの研究に賛同頂ければ、皆さん自身も研究に参加することができます。研究を身近なものとして感じて頂ければ望外の喜びです。
このホームページが皆様のお役に立つことを心から願っています。

講座紹介
生理学は、基礎学・臨床学の垣根を越えて、機能の側面から「人体の生命現象」を研究する学問で、当講座は、一貫してその真理を追究してきました。
初代(寺嶋眞一教授、昭和58年4月~平成15年3月)
専門分野:電気生理学、感覚生理学。
研究課題:赤外線感覚系の生理学と神経組織学、脳内の化学伝達物質。
研究業績:マムシ類の温熱を感じとる仕組みという赤外線受容器の発動器電位を発見し、さらにこの受容器の組織学および鋤鼻系一次中枢における解剖学的・電気生理学を明らかにしました。
受賞:井上学術賞「マムシ類の赤外線受容器の生理学的研究」。
二代目(酒井哲郎教授、平成15年~平成31年3月)膜電位の光学測定法、心臓、中枢神経系
膜電位感受性色素を用いた「膜電位の光学測定法」という強力な実験技術を駆使して、心実験的心房細動“tachycardia-like excitation”における興奮伝播パターンの解析を行なった。また、膜電位の光学的測定法の感度・時間空間分解能を改良するため、新しい測定システムの開発を受光素子と光学系の両面から積極的に推進した。
三代目(宮里実教授、平成31年4月~)排尿生理、神経生理
スタッフ紹介

教授:宮里 実 Minoru MIYAZATO
- 1987年 長崎青雲高等学校卒業
- 1993年 琉球大学医学部医学科卒業
- 1993年 琉球大学医学部附属病院 泌尿器科医員
- 1993年 東京都立清瀬小児病院 泌尿器科医師
- 1997年 琉球大学医学部附属病院 助手
- 2002年 国立療養所沖縄愛楽園 医師
- 2006年 6月~2008年 5月 米国ピッツバーグ大学泌尿器科留学(ポスドク)
- 2009年 東北大学大学院医学系研究科 助教
- 2011年 琉球大学医学部附属病院 講師
- 2015年 琉球大学大学院医学研究科 腎泌尿器外科学講座 准教授
- 2019年 琉球大学大学院医学研究科 システム生理学講座 教授 現職
- 宮里 実 (Minoru Miyazato) - マイポータル - researchmap

助教:上條 中庸 Tadanobu KAMIJO
- 2002年 長野県立松本県ヶ丘高等学校卒業
- 2014年 玉川大学大学院 脳情報研究科 脳情報専攻 博士課程後期 修了
- 2014年 自然科学研究機構生理学研究所 生体膜研究部門 NIPSリサーチフェロー
- 2015年 東邦大学医学部 解剖学講座生体構造学分野 助教
- 2017年 株式会社アイフォースコンサルティング システムコンサルタント
- 2020年 琉球大学医学研究科 システム生理学講座 助教 現職
- 上條 中庸(Tadanobu KAMIJO) - マイポータル - researchmap

助教:黒部 匡広 Masahiro KUROBE
- 2001年 明治大学付属明治高等学校卒業
- 2008年 三重大学医学部医学科卒業
- 2008年 聖路加国際病院 初期臨床研修医
- 2010年 聖路加国際病院 泌尿器科医員
- 2011年 日立総合病院 泌尿器科医師
- 2013年 筑波大学附属病院 腎泌尿器外科 チーフレジデント
- 2014年 筑波大学附属病院 腎泌尿器外科 病院講師
- 2017年 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 疾患制御医学専攻 博士課程修了
- 2017年 筑波メディカルセンター病院 泌尿器科医員
- 2018年 2月~2020年 5月 米国ピッツバーグ大学泌尿器科留学(ポスドク)
- 2020年 国際医療福祉大学成田病院 腎泌尿器外科 講師
- 2021年 国際医療福祉大学病院 腎泌尿器外科 講師・医長
- 2024年 琉球大学大学院医学研究科 システム生理学講座 助教 現職
- 黒部 匡広 (Masahiro KUROBE) - マイポータル - researchmap
令和7年10月1日現在
- 技術専門職員
- 上原 仁志 照屋聖美(研究補助員)
- 大学院生
- 秋元隆宏(東京大学泌尿器科)
- 客員研究員
- 町田 典子、長嶺 覚子、樋口 裕城、鈴木 智晴、泉 惠一朗、川満 勝一、鶴岡 マリア、長嶺 ふじ子
- visiting researcher
- 泉晃(株式会社ボストン コンサルティング グループ データサイエンティスト、先端医学研究センター R3クロスアポイントメント)
- 非常勤講師
- 細川 浩、梁 運飛、秋山 佳之 (信州大学泌尿器科 教授)
受賞
- 2026.01.24 第139回日本泌尿器科学会沖縄地方会において黒部匡広先生が優秀演題賞を受賞しました。
- 2023.10.07 第76回日本薬理学会西南部会において川瀬紘太先生が若手研究者奨励賞を受賞しました。
- 2023.09.08 第30回日本排尿機能学会(千葉)にて川瀬紘太先生が河邊賞を受賞しました。
- 2023.02.06 大学院生 長嶺覚子先生(令和5年3月修了)学生表彰(学長賞)
- 2022.03.15 樋口裕城先生 ISDN(International society for developmental neuroscience)のtravel award
- 2021.04.28 大城琢磨先生 第8回琉球医学会優秀論文賞
- 2021.01.12 助教 上條中庸先生 令和2年度 公益財団法人沖縄県医科学研究財団 研究助成
特許
1.名称:脊髄オピオイドμ受容体を介した新規腹圧性尿失禁薬剤
- 発明者:宮里実、芦刈明日香
- 権利者:国立大学法人 琉球大学
- 種類:特許
- 番号:特願2018-229643
- 出願年月日:平成29年12月8日(承認:令和4年10月31日)
- 国内外の別:国内
2.名称:膀胱機能障害を有する生体に対する低出力体外衝撃波による治療装置及びこれに使用する衝撃波照射プログラム
- 発明者:宮里実,大城琢磨,上條中庸
- 権利者:国立大学法人 琉球大学
- 種類:特許
- 番号:特願2022-135480
- 出願年月日:平成4年8月29日
- 国内外の別:国内
3.名称:骨盤底ヘルス
- 発明者:宮里実,芦刈明日香,長嶺覚子,阿部正子
- 権利者:国立大学法人 琉球大学、公立大学法人名桜大学
- 種類:商標登録
- 番号:商願2014-103216
- 出願年月日:平成6年11月28日
業績
代表論文
Ashikari A, Miyazato M, Kimura R, Oshiro T, Saito S. The effect of tramadol on
sneeze-induced urethral continence reflex through μ-opioid receptors in the spinal cord in
rats. Neurourol Urodyn 2018 37(5):1605-1611.
要約:オピオイド受容体の中でμ受容体が尿禁制反射を増強することを解明した。本論文の要旨は、第70回西日本泌尿器科学会総会(2018年) ヤングウロロジストリサーチコンテスト優秀賞を受賞した。
Kimura R, Miyazato M, Ashikari A, Oshiro T, Saito S. Age-associated urethral
dysfunction in urethane-anesthetized rats. Neurourol Urodyn 2018 37(4):1313-1319.
要約:加齢に伴う一酸化窒素(NO)の低下が尿道弛緩反応の減弱の原因として示唆された。加齢に伴う残尿、尿閉といった膀胱機能障害の機序として初めて尿道に着目した本報告の意義は大きい。
Oshiro T, Miyazato M, Saito S. Relationship between connexin43-derived gap junction proteins
in the bladder and age-related detrusor underactivity in rats. Life Sci. 2014 116:37-42.
要約:加齢に伴う排尿筋低活動の成因として、膀胱平滑筋細胞間結合蛋白コネキシン43の減少による情報伝達の低下が原因の一つであることが初めて証明された。本論文の要旨は、Second
Prize Winner of the 2015 Annual Jack Lapides Essay Contestを受賞した。
上條代表論文
Kamijo TC, Miyazato M. The influence of maternal separation on the development of voiding and
behavior in rat pups. Continence. 2022 5:100570.
要約:ラットを用いて幼少期ストレス(母子分離)は成長後にでそれぞれ排尿行動と膀胱活動に影響を及ぼすことを示した。
Kamijo TC, Hayakawa H, Fukushima Y, Kubota Y, Isomura Y, Tsukada T, Aihara T. Input
integration around the dendritic branches in hippocampal dentate granule cells. Cogn
Neurodyn. 2014 8: 267-276.
要約:海馬歯状回顆粒細胞の樹状突起分岐部では、特定の入力が非線形的に統合されていることを発見し、そのメカニズムを解明した。1つの細胞の局所でも効率よく情報統合が成されていることを示した。
黒部代表論文
Takaoka EI, Kurobe M, Yoshimura N, Chermansky CJ, et al. Urethral dysfunction
and therapeutic effects of a PDE 5 inhibitor (tadalafil) in a rat model of detrusor
underactivity induced by pelvic nerve crush injury. Neurourol Urodyn 2020 39(3) :
916-925.
要約:PDE5阻害薬は骨盤神経損傷によるラット低活動膀胱モデルの尿道弛緩反応を促進させる事で残尿が減少させ、排尿効率を改善させる事を立証した。本論文の要旨は、全世界で公募される排尿機能研究の論文コンテスト「DIOKNO-LAPIDES
ESSAY CONTEST」にて2位に入選した。
Kurobe M, Kawai K, Suetomi T, Nishiyama H, et al. High prevalence of hypogonadism determined
by serum free testosterone level in Japanese testicular cancer survivors. Int J Urol 2018
25(5) : 457-462.
要約:精巣腫瘍治療後長期生存者におけるQOLや性腺機能低下について検討し、患者群では遊離テストステロン値が有意に低い事を本邦で初めて報告した。本論文の要旨は2016年度の日本性機能学会トラベルグラントを受賞した。
Kurobe M, Kojima T, Nishimura K, Nishiyama H, et al. Development of RNA-FISH Assay for
Detection of Oncogenic FGFR3-TACC3 Fusion Genes in FFPE Samples. PLoS One 2016 11(12) :
e0165109.
要約:FGFR3遺伝子変異やFGFR3-TACC3融合遺伝子は尿路上皮癌の発生に関与している。RNA-FISH法を応用してホルマリン固定パラフィン包埋組織(FFPE)から同融合遺伝子を検出する方法を初めて確立した。